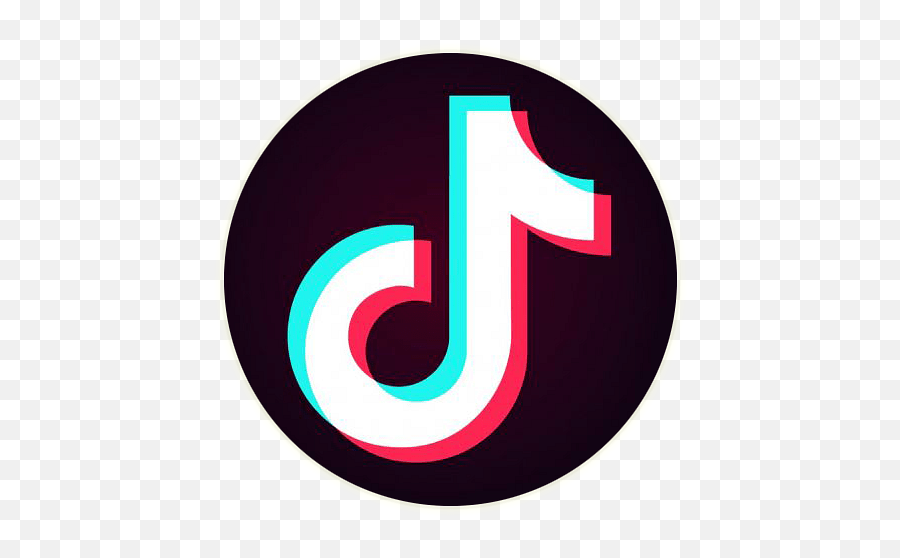令和2年1は、コロナ禍という既存体制を疑うに十分な材料を与えられながら、「終に何も起こらなかった年」となった。
一昨年まで、我々は、明らかな不正義に直面していなかった。黒船への危機感や旧弊への苛立ちはなかった。娘を売る貧農や斬られるべき君側の奸もいなかった。人民が蜂起の気を起こさない第一の理由は、少なくとも形式的には自由で平等な社会が現実となっているからだ。それなりの教育機会と生活とが保障されていながら、万が一にも路頭に迷うようなことがあれば、それを「当人の自己責任」と片付けることが可能である今日、もし街中に革命歌を謳う者が居たら、共産趣味者か、かなりの変人と見做されるだろう。
さりながら、令和の世にも、誰しも、何らかの「生きづらさ」を感じないだろうか。否、いかなる時代においても、多少なりとも生きづらさを感じない者は、余程の蒙昧か、何らかの理想に傾倒しているかだろう。自然人の幸福から独立した「不自然な規範」は、市民の名誉と身体、通貨とを法によって覊束する近代国家は、個々人に生きづらさを与えるのが必定である。問題とするべきは、その生きづらさをどこまで許容するのか、そして許容できない生きづらさをどこまで解消するべきか、である。
視座を権力者側に移すと、時運の趨く所2川の流れのようにおだやかに身を任せていたい3日本国には、不安を基調とする拡張の欲求が描いてきた人類史を、力強く歩む気概を見いだせない。私は、個人の権利と施政の権力とが調和された近代国家には、誕生から数百年を経た今日も、また向こう数十年も、人類史における役割を期待している。近代国家は、知恵の実により反自然の業を負った人類が、平和と発展とを両立させるための綱渡りの棒だ。一般的にその範囲として、ここ数百年で定義された国民国家の領域がある程度妥当であり、日本において日本列島がこれに当たる。しかし、多国籍企業との相対という直近の課題や、侵略からの防衛という息の長い使命について、主体的な策を講じられないほど疲労しているように思われる。
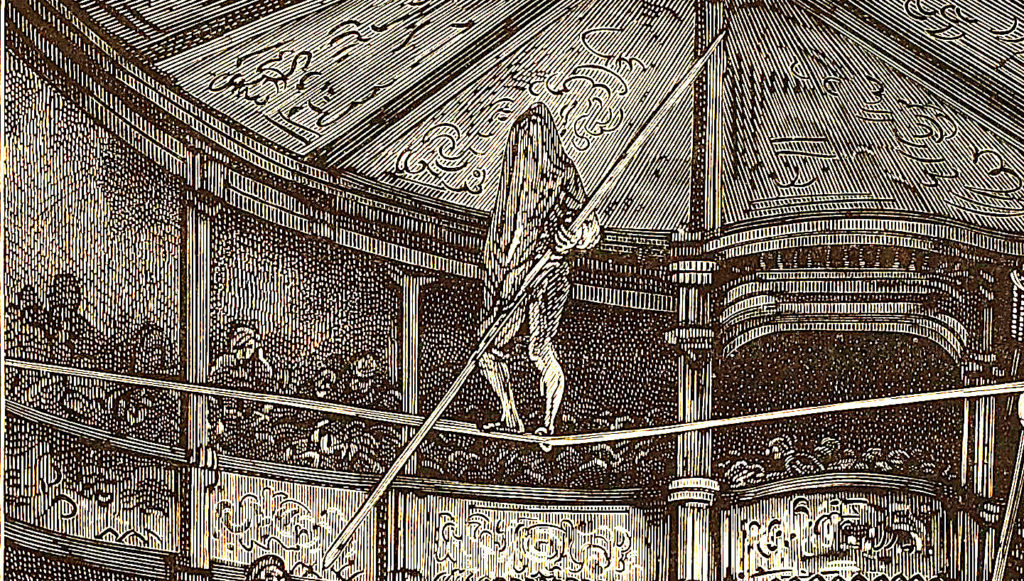
私は、「東京を玉将とする構造」が、今日の生きづらさと日和見主義とを醸成していると考える。総力戦を遂行するための「非常体制」は、東京を居城とする権力者たちに、終身雇用年功序列に安心したい人々の心に、残存している。昭和の体制は、革新官僚が緻密に構築していたので、「理想の人生」が困難となった平成の世に入っても、若者に特有のはずの冒険心を削ぎ、大いなるものに対する挑戦の気概4を損ないながらも、現秩序の支持を至高とする気質を培ってきた。
金甌無欠や宇気比のごとき清浄5を制度に求めると、抑圧的で硬直した政治を生起させやすくなる。人が創る制度には、必ず欠缺が潜む。不完全さを前提とし、環境の変動に応じて軌道を修正する余力を持たせた政体の方が健全である6。日本社会の「空気の支配」に注目するとき、私は、天皇の下での三地方への分権分散こそ、日本を維持しながら軌道修正を上手く働かしむる政体と考える。現代の日本人が創り出せる政治機構は、「日本国政府」だけでは無い。同じ君主を戴く異なる三つの政庁が、日本語を基調として存在することは、日本人の触れる空気の幅を広げる。他の二政庁は、改革の希望であり、競争相手なのだ。内戦や敗戦、あるいは革命に頼らないでも、自己改革が可能な時代に入りたい。
憲法改正を使命と掲げた安倍晋三は、終に憲法改正を発議しなかった。真に「自主憲法」を望み、理想の憲法は空気が支配する民主的政体を採る日本国に実現されないという諦めに立つのならば、コロナ禍に乗じて、あるいは宰相の体調不安に託けて、権力内部の「自浄作用」が働くものだ。平成と令和とに跨る9年間は、この権力者達は、力を使いこなす気概はないが、「緊急事態宣言」「特定秘密」「存立危機事態」というおどろおどろしい文言を用いた法統制は好むという性を証明したものだった。
私は、目隠しの綱渡り師に覇道を歩ませたくないので、彼が握る棒をかかる臆病な集権主義者達の恣にされることを望まない。太平の裏は、若者の活力や多様な人々を受け容れる王道7を行きたい。
註釈
- 西暦2021年
- 小堀桂一郎「『終戦の詔書』成立の舞台裏 安岡正篤の寄与を焦点に」ほか、関西師友協会編『安岡正篤と終戦の詔勅 戦後日本人が持つべき矜持とは』、株式会社PHP研究所、2015年
- 秋元康『川の流れのように』。昭和と平成との分け目に世に出たことは象徴的である。
- 維新の志士といった体制への挑戦者のみならず、新規領域が生じた際の起業家や新地(北海道、南洋諸島、アメリカ大陸、外地など)への開拓民もまた、冒険心の漲る大いなるものへの挑戦者であった。
- 三島由紀夫『豊饒の海』第2巻「奔馬」
- 米国における二大政党が争う大統領選から、タイ王国における立憲君主制を基調とする毎度の軍事クーデターまで、実に多種多様である。
- 太山は土壤を讓らず、故に能く其の大を成す。河海は細流を擇ばず,故に能く其の深を就す。王者は眾庶を卻けず、故に能く其の德を明らかにす。
司馬遷『史記』巻87「李斯列傳 第二十七」