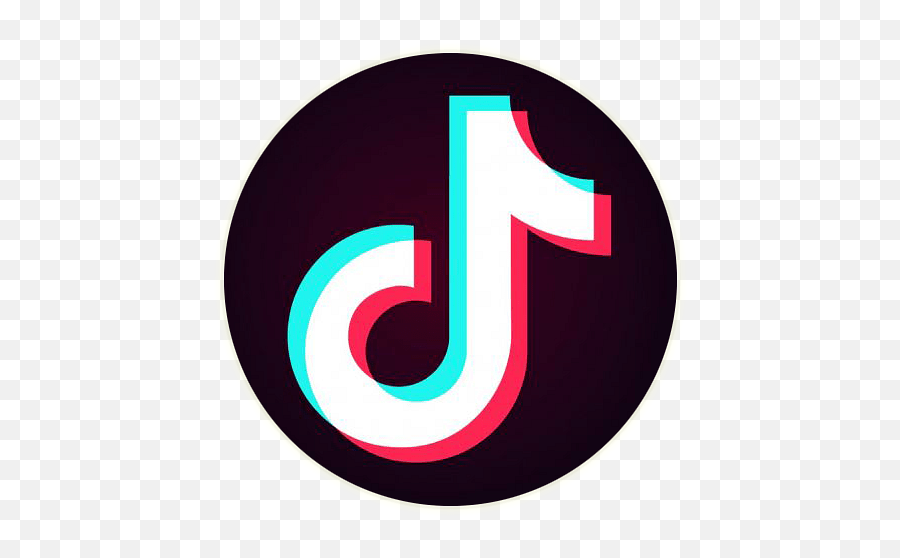通勤電車に揺られていると、数メートル先で、人がしゃがみこんだ。
つい先日電車内で吐瀉に遭遇したことを思い出して一抹の恐怖を覚えたが、人込みをかき分け近づくと、カバンには赤いマークがあった。当人は、発話こそ儘ならなかったが、質問に頷くことはできた。幾つかのクローズドクエスチョンで、座れば落ち着くことが判ったので、席を譲ってもらう。体が震えているが、「長時間立っていると気分が悪くなります。座れば落ち着きます」とのメッセージカードを指示するので、様子を見ることにした。
程なくして次の駅、駆け付けた駅員は遠巻きに下車を勧めたが、当人は再びメッセージカードを指示するので、事情を説明し、乗車を継続。同じ下車駅に近づくころには、大分落ち着いたようで、乗り換えホームまでゆっくりと歩いて行った。

ヘルプマークは、認知不足が課題として指摘されるが、認知が広まったとて抽象的な記号に過ぎない。より重要であるのは、社会的ないしは世間的に規定されるこの記号の意味だ。今回の事例は、助ける者が「感染症ではないか」「判断を間違うのではないか」と怖気づいるところ、ヘルプマークとメッセージカードとが勇気を与えたというものである。「ヘルプマーク」と検索すると、公共機関の広報サイトが優先的に出てくるが、同時に「悪用」のキーワードも提案される。また、紋切型のまとめサイトの多くは、問題点を指摘するような論調が強いようだ。本事例が、ヘルプマークという記号の意味を規定するものとなれば幸いである。
さて、当人がしゃがみ込んだ時、横に立つ者も、目の前に座る者も、誰も、何もしなかった。この瞬間は、非常に悲しかった。当人に近づこうとして満員電車でよくあるように押し返されたとき、しかし「大丈夫ですか?」と大声を出すと、さっと道が開けた。大声の会話で状況が明らかにされると、複数人が席を譲った。
平和を保ちたい心はときに無関心を伴う、しかし切っ掛けがあれば、助けを求める声に応えて温かい手を差し伸べるように変わる。記号や一声には、一人でも多くの者が、より自由に生活できるようにする力がある。
温かい社会は、未来の可能性が広い。標準化された心身から外れるものをも包摂する社会こそ、私は豊かな社会であり、長期的に靭い集団であると信じる。